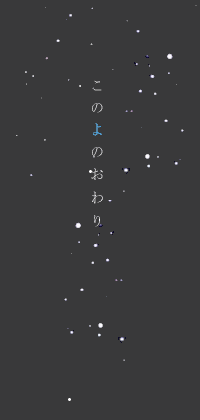何よりもの絶望は、多分、それが当然の如く隣で生きてしまっている事だった。この手は既に赤い感覚を食んで生きる事に懐疑を忘れ、常のように腐爛した脂の臭いをその身に纏っている。それを脳が意図も容易く甘受してしまったから、心も群れを成す雁の様に、それに倣った。嘆きも無ければ祈りも無い。ただただ、そうして日々を消光し、想いさえも静かに歪んで、消えて行く。 想う事など何も無かった。神無月を迎えるとこの街が、全ての街が、橙の香りに満ちる事と同じようにそれは普遍で、当然で、平生で、呼吸も同じで、特別に存在すらしていなかったのだから。 死んでいたのだ。ひとつひとつの世界を殺す度に、自分もまた、醜く、無様に。
が口を開けば里の人間は忽ち一目散に何処かへ逃げて行き、子ども達は時に目を輝かせてそのままそこに居座り、時に恐れ戦きやはり一目散に何処かへ逃げて行く。は言葉遊びとその言葉遊びに巻き込まれ首を捻り窮する人間を見るのが好きだという、凡そ花屋の娘に似付かわしく無い屈折した趣味を御持ちで、その能弁をつらつらと垂れ流す様はまるで何処か違う世界から使わされた預言者のようであった。は、今日はいい天気ですねとその一言を言えば良い事を、捻じ曲がり一度離れてもう一度戻ってくるような言い回しで話す。の形の良い唇が言葉の欠片を象ったら、俎上の魚も同じ。生きて帰る事は出来ない、なんて大袈裟な事になりはしないが、少なくとも、身も心も脳も何もかもが疲労困憊に陥るので、に自ら近付くような物好きな人間はこの里に誰一人として存在していなかった。俺以外。 は花屋の娘であるのだから当然花を売り、花と起臥を共にしている。売り手に問題があっても花にはなんの罪も無い。それにの売る花はどれも見事に美しいものだから、客はの性格を知った上でそれでも花を求め、店に足を運ぶ。しかし誰もが長居は無用とばかりに、さっと花を受け取りさっと金を置いてさっと帰って行く。そのまるで密売人のようなやり取りは、花屋の概念を覆す異様さで満ち溢れていた。 誰もがを倦厭し、沈黙を望む。けれどもにとってはそれこそが、何よりもの愉しい事なのかもしれない。笑いながら花に水をやるを見ていると、なんとなく、そんな気がした。 「」 「あれ、こんばんは、私のお陰か自分のお陰かは定かではないけれどもこの里一番の物好きと名高い天才忍者のはたけカカシくん。おつかれさま」 「………こんな時間に水やり?」 良い子はとっくに眠る、おどろおどろしい丑三つ時に、花屋の娘はその売り物に魔法をかけるのか? 下らない事を思っているとがえらく愉しそうに笑うものだから、ああ捕まったな、と思った。俺以外の人間は此処で絶望し、自分にぐるぐると巻き付く見えない縄を必死に取ろうともがく魚になるのだけれども、それを甘んじて受ける俺は確かに、この里一番の物好きなのかもしれない。でも仕方がないのだ。の事が好きなのだから、こればっかりは、仕方ない。 の唇が動く。今この瞬間、誰もが沈黙等というせん劣は、許されない。 「月夜に光る水の煌きとはなんとも神々しく神秘的で、此処まで綺麗だと何か不思議な力があるのではないかと思い至ってね。そうすると私が普通に育てても普通に美しくなる花がもっと美しくなるのではないかと考えると、それは花にとっても嬉しい私にとっても嬉しい、良い事尽くめではないかと、そう思うと居ても立っても居られなくなってしまって、つい先程布団から飛び起きてそのままの勢いで水やりしているのだけれども、やはり私の仮説は正しかったようで御覧よこの植木鉢、さっきまで蕾だったのにもう花開いた。まあ、嘘だけど。」 「………それは、」 一体何処から何処までが、そもそも何が嘘なのか解らない。相変わらずだなあと溜息を吐くと、がけらけらと笑って如雨露を傾けた。水が月光を浴びて宝石の様に輝き、今咲いたなんて戯言で示した花に落ちて行く。確かに、それは神々しく神秘的で、何か不思議な力がありそうだと思った。それは、嘘じゃない。 「綺麗だな」 そう言うとが珍しく驚いた顔をして数回瞬きを繰り返すものだから、俺も一体何にそんなに驚いたのか理解出来ずに同じように驚いてしまい、少し瞠目する。何時も大きく開かれる口はぴったりと閉ざされ、その代わりに大きく見開かれた目玉がいつもの言葉のようにころころと零れ落ちそうだったので、今日は来ないほうが良かったのかもしれないな、となんとなく辟易しながら、逃げるように如雨露の水を見続けた。 ぽたりぽたり、滴り落ちる小さな雫が、名前も知らない花に落ちていく。それはやはり神々しく神秘的で、宝石のように酷く、美しく見えた。 「………狐、」が言う。「狐?」「きつね」が指で狐の形を作り、コーン、と鳴いた。あまり似ていない。 「狐の嫁入りに人々は感嘆を吐くが、角隠しの下には果たして何が在るのだろうか。帳の中の灯篭は、決してその色では無い。という話があるのだけれども、カカシ、知ってる?」 「知らない」 「だろうなあ、だって今作った」 「………」 うけけ、とが悪魔のように笑う。随分前に子ども達の間で「花屋の娘は実は悪魔である」という可愛らしい噂がたっていた事があったけれども、成る程確かに笑い方はそれそのものである。けれどそれ以外、悪魔の要素なんて何も無いという事を、きっと、俺以外誰も知らない。程優しい人間は居ないと、常日頃思って止まない事を言えばこの里の人たちは一体どんな顔をするのだろうかと考えて、きっと、物好きの与太話が始まったと、皆それこそ悪魔のような顔で俺を見るのだろうな、と思った。それは、最早たったひとつしか生きていない、死んでいる俺を見る人間と同じような、顔で。 ぽたり、と如雨露の先から水が滴り落ちる。花びらの上で、それは赤く赤く、爆ぜた。 「小判を持った猫がひとつ鳴く。かわいそうに、こちらをお食べ。差し出されたものは果たして真実なのだろうか。楠の下の小さな湖も、決してその色では無い。死に損いのヴァイオレンスはその種だけである。此処まで純粋なのは、その種だけ」 「………」 「この世は生きている限り醜さから脱却出来ない生き物で溢れかえっている。どれだけ泣き叫ぼうが喚こうがそこはきっとずっと腐ったままで、どれだけ綺麗なものをその身に繕おうがそこはきっとずっと、醜いまま。誰もが、そうだなあ、この如雨露から出る水の様に美しくありたいと願うけれども、結局どうすることも出来ないし、最後は何もかも同じところに行き着くのだから意味なんて、無い」 「………それで、結局何が言いたいの?」 「結局?結局、そうだなあ、結局何が言いたいのかと問われると、カカシ、君には非常に残念な話なのだけれどもね、」 月がの顔を照らす。俺は光の当たらないところへ。 花屋の娘は丑三つ時に、一体誰の釘を刺す? 「この世に綺麗なものなんて何も無いんだよ」 何も、なにも、なんにも、無い。が踊るように喋ると、不思議と俺も踊るように、影から出れた。夜は未だ終わらない。敵なんて始めから何処にも居ないと教えているのに、須らく俺の味方する夜がいま初めて、敵を、見失った。 「この世は面白いくらいに平等で、誰も変わりやしない。カカシ、悲観してはいけないよ。だからといって、君は忘れてはならない。真意と、それだけの数を、忘れてはならない。それだけで、きっと、良いんだよ」 里の者は言う。花屋の娘が口を開けたらお逃げなさい。言葉に耳を傾けてはならないよ、二度と戻って来れなくなってしまうから。花屋の娘がまたおかしな話をしている。花屋の娘は優しいよ。花屋の娘はどうにも狂気染みている。何を言っているのかさっぱり解らない。花屋のお姉ちゃんは本当は悪魔で、普段のあれは仮の姿をしているんだよ。花屋の娘は多分、少し、病気なんだろう。花屋の娘はそうね、とても個性的よ。この間お店に行ったら花屋の娘に捕まって。花屋の娘は優しいよ。花屋の娘は性質が悪い。けれどもあそこの花は、とても、きれいだ。 「だけが、優しいよ」 「カカシだけが物好きだよ」 血まみれのこの身体を、が撫でる。乾いた命の欠片が、ぱらぱらと光りながら、落ちていった。確かにこの世に綺麗なものなんて何も無い。の言葉は真理である。それでも、如雨露の水は、落ちた欠片は、の花は、ただ、綺麗だった。 「俺は悲観なんかしてないよ。出来もしない。けれど、そうだな、間違いなく、人を殺すために殺してなんて、いない」 花屋の娘は丑三つ時に、誰の釘も刺さない。魔法もかけない。ただ、光の中で、真っ赤な絶望の、腕を抱く。 「そんなこと知ってるよ。………仕方ない、この里一番の物好き忍者カカシくん。君には、否、君だからこそ、この世で唯一、ほんの少しだけ、雀の涙よりも小さいけれども確かに存在しているたったひとつの綺麗なものを、特別に教えてあげようじゃないか」 が笑う。里の人間誰もが一目散に逃げ出して行く顔で。 「だから、ほら、カカシ。そのままで良いから、こっちへおいで」 けれども今日逃げ出したのは、夜、ただ一人だけだった。 「このよの、おわりだ」 |